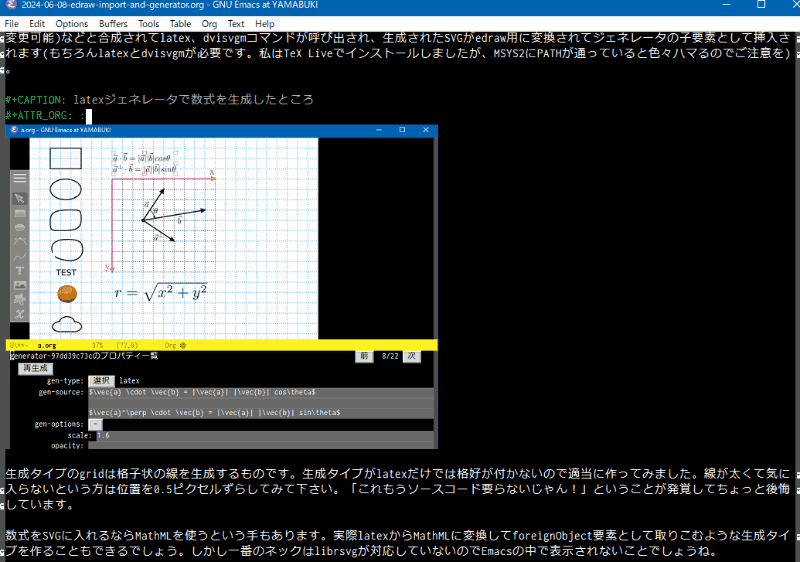org-modeで C-c C-j (org-goto) を実行し、日本語(マルチバイト文字)を入力すると次のようなエラーが出てインクリメンタルサーチできない(Org9.7.3時点)。
funcall-interactively: Wrong type argument: stringp, [12375]
consult-org-heading なり consult-outline なりを使えば良いような気もするけど気持ち悪いので一応直しておく(org-goto-local-auto-isearchに対する修正)。
;; org-gotoで日本語検索が出来ない問題を修正 (with-eval-after-load "org-goto" ;; 関数を置き換える。 (defun org-goto-local-auto-isearch () "Start isearch." (interactive) (let ((keys (this-command-keys))) (when (eq (lookup-key isearch-mode-map keys) 'isearch-printing-char) (isearch-mode t) ;; ここから修正 ;; 元: (isearch-process-search-char (string-to-char keys)) (cond ((vectorp keys) (when (< 0 (length keys)) (let ((ch (aref keys 0))) (when (integerp ch) (isearch-process-search-char ch))))) ((stringp keys) (isearch-process-search-char (string-to-char keys)))) ;; ここまで修正 (font-lock-ensure)))))
this-command-keys はキーシーケンスを文字列で返すこともあればvectorで返すこともあるのだとか(Strings of Events (GNU Emacs Lisp Reference Manual))。